| |
“石の街並みを守る。創る。”事業が動きだしています。
これからホームページに連載する形で、石の街並みの背景や由来などを説明して行きたいと思います。阪神間モダニズムと呼ばれる文化を生んだ街を訪ねましょう。第1話目はトーマス・グルーさんという外国人技師に天国から登場してもらい語って頂きましょう。一体誰? その訳は?彼はこのあたりが住宅地、或いは邸宅地として発展するその訳を語ってくれます。キーワードは明るさと清潔さ(山、海、太陽、そして御影石)、そして住吉駅です。
まだちょんまげの明治初期、新政府は近代化の象徴として外国人の手を借り鉄道敷設を急ぎました。グルー氏は来日し大阪神戸間の官営鉄道敷設を指揮しました。彼は神戸再度山の修法が原外人墓地に眠っています。さて、グルーさんの登場です。(史実をもとにフィクション化しています。)
私の名前はトーマス・グルー。英国人の技師で、今、日本に来ている。
今から7年前、この国はミカドの政府になり、それ以降すさまじい近代化が進められている。私も、ミカドの“お雇い外国人”として大阪神戸間の官営鉄道敷設を指揮している。1870年に工事が始まりやっと今日、1874年6月1日開業まで漕ぎ着けることが出来た。ミカドの暦では明治7年6月1日。
私は、官営鉄道住吉停車場にいる。今日はその開業式があるのだ。工事を思い出し感慨にふけっている。芦屋川、住吉川、石屋川は天井川で、地面から盛り上がっており、官営鉄道は川床の下にトンネルを掘り線路を通した。そして、住吉川を越えた線路は扇を描くように右に緩やかにカーブし住吉ステーションに着く。住吉川が六甲山地を抜けて平野に出ると天井川となり、いくつも大扇状地を形成しつつ南の大阪湾に向かいかなり急な斜面を形成している。鉄道を通すにあたっては、扇状地の等高線に沿って線路を敷設したため緩やかな大カーブとなってしまった。
そんなことを思い出している。しかし、この景観のすばらしさはどうだ。英国のどんよりと曇った空からは想像できないくらいこの国は明るい。このあたりの風景は、それ自体、神が民にごひいきをされたのではないかと思うくらい息を呑み見とれてしまい、溶け込みそうになる。
緑の六甲、きらきら光る海、東から西へ長く続く田園。何本かの川が海へそそぐが、天井川の堤と松並木がいい。住吉ステーションのすぐ東、住吉川の土手から西を見ると、それはすばらしい眺めである。マヤ山に落ちる夕日もいい。
さて、この鉄道だ。私はこの住吉ステーションを軸にすばらしい住宅地が形成されると見ている。何度でもいうが、年中、太陽が照る温暖な南向きの斜面、ゆったりと屋敷地を構え、前に海、後ろに山並みを取り込む。そして私が決定的に思うのは、六甲の風化花崗岩が持っている清潔さである。白い色、淡いピンク石。日本人達は元来きれい好きであり、ミカゲ石と言う名で全国に出荷されているのもうなずける。住吉川の川原の白さ、清冽な水、きらきら光る里の白い道。砂浜もいい。何という明るさ、美しさだ。
神戸の居留地の外人たち、それに大阪の豪商たち、住吉ステーションなら毎日通える。
ハイカラな石の街並み、そこに住む市民ブルジョアジー達。これだけ揃えばきっと文化が花開くと思う。日本人は欧州に比肩する高度な文化を持っている。100年後、どんなモダニズムが花開いているのだろうか。見てみたいものだ。
酒造家たちが汽車の煙で酒がにごると反対した海岸沿いのルートを断念し、技術的に困難であったがムコ、ウハラの野辺の真ん中を通した事も将来を思うと良かったかも知れない。
さあ、下りの大阪発の一番列車がまもなく住吉に着く時刻だ。英国風の駅舎もこの景観だからこそで、ぴったりだ。うれしい。
あっ、見えたぞ。住吉川トンネルを抜けた蒸気機関車が。文明開化。この調子ならあっという間にミカドの日本帝国は一流になると思う。
ではまた。私もセレモニーに急がないといけないので。
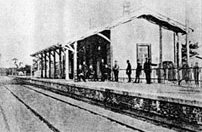 |
 |
住吉駅と阪神間開通最初に使用された機関車
出典:『すてんしょ 阪神間開通80週年記念』 田中精一編
出版 國有鐵道大阪驛 刊行年 1954年 |
|
|